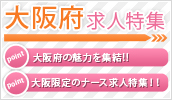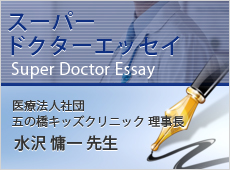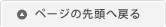第67回 黒岩裕治の頼むぞ!ナース
黒岩祐治の頼むぞ!ナース

第67回 ~親友の死と生きる意味~

友達はたくさんいても、人生の上でほんとうの親友と呼べる存在というのは、せいぜい1~2人でしょう。私にも2人の親友がいました。そのうちの一人が先日、亡くなりました。ちなみにもう一人はすでに4年前に51歳で亡くなりました。結局、僕の親友はいなくなってしまいました。生まれも1週間ほどしか違わない私と同じ56歳。浪人時代に知り合ってすっかり意気投合。以来、36年間。今も家族ぐるみで付き合う大事な大事な親友でした。
朝、胸のあたりが痛いと訴え、奥さんにマッサージをしてもらった直後、突然、心臓呼吸が止まったというのです。高校3年生の長女は「パパの息が止まる音を聴いた」と言っていました。その彼女が即座に心臓マッサージをし、駆けつけた救急救命士が除細動をしたけれど、鼓動は再開することはありませんでした。未だに死因は特定されていませんが、心臓の疾患だったことは間違いありません。
彼女は大学受験の真っ最中。父親が果たせなかった医師への夢を受け継ごうということなのか、医学部をめざしていました。私も彼女を赤ん坊の時から知っていますが、美しく、清楚で、聡明で、成績もよく、しかも父親譲りの心根の優しい素晴らしい女性に育っていました。
将来、彼女が医師となって働いていく上で、父の心臓を動かそうと必死になったこの時間はきっととても大きな意味を持つことになるに違いありません。しかし、まずは当面、この衝撃を乗り越えていけるかどうか…、私は祈るような気持ちです。
なんの予兆もない、まさに突然の死でした。長い付き合いの中で、彼が病気をしたという記憶が私にはありません。スポーツ万能で、がっちりした体格で、いかにも頑丈そうな男でした。それがスイッチを切るように、いのちを終えてしまったのです。下の長男はまだ小学6年生。崩れ落ちそうな母親の傍らで、気丈に振舞っている姿に胸を掻き毟られるような思いでした。
実はこの長男が1歳の時、インフルエンザワクチンの副反応によると思われる病気で、この一家はたいへんな思いをしていました。有名な大学病院に入院したにも関わらず、原因が分からないと言われ、薬の投与が続けられていました。一向に薬が効く気配がないことから、どんどん強い薬に変えていかれました。
症状はよくなるどころか、むしろ悪化の一途をたどり、ついには「悪魔が乗り移ったかと思った」というように、自分で自分の頭をベッドに打ち付けたりという異常な行動を取るまでになったのです。さらに強い薬に変えようと勧められたところで、我が親友の必死の闘いは始まりました。
ボストン在住の高校の同窓生のドクターに相談を持ちかけたのです。その同窓生の夫人もドクターで、親友からのメールに夫婦がチカラを合わせて対応しました。その膨大なメールのやりとりのコピーは私の手元にありますが、親友が長男の病気にどれほど真剣に向き合っていたか、その気迫が伝わってきます。
今ここで詳細をたどることはしませんが、要するにこの海を越えたメールのやりとりによって、長男の病気は治ったのです。結論を言うと、「もしかしたら薬が原因かもしれない」というドクター夫妻のアドバイスに従ってすべての薬の投与を中止した結果、徐々に快方に向かい始めました。
アメリカでは「薬が効かなかったら薬を疑え」というのが、臨床現場での常識なんだそうです。彼らが分析した過程で類推したのは、新たな薬の投与によって新たな症状が出てどんどん悪化しているが、その新たな症状はその前に飲んだ薬の副作用ではないかということでした。
もともとの病気が特定できないままに進んだ治療でしたが、ドクター夫婦はある病気を疑いました。もしその病気だとすれば、正しい対処法は「放っておく」ということだったのです。それは時間が経てば自然に治る病気です。二人は患者を直接、診断もしていないわけですから、確信は持てません。しかし、親友は直感的に「その指摘が絶対に正しい」と感じたそうです。
親友はそのアドバイスに従って、主治医に掛け合いましたが、当初は当然のごとく激しく抵抗されたそうです。主治医にしてみれば、診察もしていない海の向こうのドクターの指示に従えと言われても、責任は誰がとるのかということで、安易に受け入れられる話ではありませんでした。
「親として私が全責任を負いますから、薬を止めて下さい」親友は有無を言わせない迫力で迫りました。主治医はそこまで言われたら…と、もはや従うしかありませんでした。それは大きな賭けではありましたが、結果的にそれが表目に出たのです。
ドクター夫婦は後から聴いて驚いたそうです。まさか急に薬を全部止めてしまうなんて想像もしていなかったと言うのです。当然のごとく、様子を見ながら少しずつ止めていくものだとばかり思っていたようです。結果的にはそのことで重大な事態につながらなかったからよかったものの、素人判断はやはり怖いです。
彼らは患者である長男を直接、診察したわけではありません。あくまで、親友から送られてくる情報だけを頼りにアドバイスを行なっただけです。それなのにどうしてこんなに的確な判断を下すことができたのでしょうか?逆に言えば、日本有数の大学病院のドクターはそばで診ていながら正しい判断ができなかったのでしょうか?
そのカギを握る存在が薬剤師でした。当時からアメリカでは臨床現場に薬剤師がいて、ドクターは薬剤師と相談しながら薬を処方するのが当たり前でした。最近でこそ、日本でも臨床現場に出てくる薬剤師は珍しいことではなくなりましたが、当時は薬局の奥にいて、医師の処方に基づいてひたすらそのとおりに薬を出しているだけというのが彼らの仕事でした。薬剤師との連携がうまくいっているアメリカにいたドクターであったからこそ、薬の問題に気づくことができたのです。
長男は完全に元気になって退院し、後遺症もなく、順調に育っていきました。親友はその成長ぶりがうれしくてならないようでした。当時のことなど全く感じさせないくらいに元気に走り回る姿を見て、いつも心の底からの笑みを浮かべていました。彼の人生は正直言ってあまり幸運に恵まれたものではありませんでした。「僕の運のすべてを息子のために使ったのかもしれない。でも、それならそれで大満足だから」いつもそう語っていました。
棺の中に眠る彼の表情は穏やかそのものでした。一瞬のことだったために、全く苦しまなかったからでしょう。おそらく彼は自分が死んだなんて思ってないに違いありません。彼にとっては一瞬、眠りに落ちただけのことでしょうから。もし、そうではなくて、自分が死ぬんだと分かった上で死んでいたとしたなら、特に6年生の子供を残してとても今は死んでいられない、死んでも死にきれないという壮絶な顔をしていたに違いありません。
よくピンピンコロリがいいと言いますが、それはある程度、生きた上でのことでしょう。最近、私のごくごく身近なところで瞬間死が二件、続きました。私の大学院の院長が会議での発言中に急死したのです。解離性大動脈瘤ということでした。彼の場合は74歳。しかも普段から仕事中にポンと死ぬことに憧れを抱いていたと言いますから、ご本人にとっては理想的な死に方だったでしょう。
しかし、親友の場合、本人は分かっていないからいいかもしれませんが、残された者がこれから背負っていかなければならない苦悩は想像を絶するものです。それでいいとはとても言えません。今、こうして原稿を書きながらも、未だに彼の死を受け止め兼ねているのが正直なところです。死を考える、生きる意味を考える、これまでも意識してきたつもりではありましたが、まだまだ何にも分かっていないことを痛感させられた次第です。(完)
 |
「黒岩の法則」 著:黒岩裕治 |