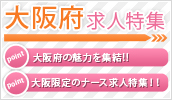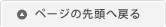第46回 黒岩裕治の頼むぞ!ナース
黒岩祐治の頼むぞ!ナース

第46回 ~「いのちの教育」と終末期医療~
私は国際医療福祉大学の客員教授として、東京青山の大学院で医療ジャーナリズムコースの講義の一部を担当しています。実は今年のクラスに異変が生じています。日本看護協会の元幹部や、看護界のカリスマ的存在ともいうような大物が院生として、私の講義に来ているのです。私より年上の方もたくさんいます。私は相当、厚かましい方だとは思いますが、このような看護のプロ中のプロたちにいったい何を教えるというのか、さすが気恥ずかしさでいっぱいになってしまいます。
村上紀美子さんは日本看護協会の元広報室長で、30年も広報を担当してきた人です。5年前からはフリージャーナリストとして取材・執筆活動をしています。私はかつて「感動の看護師最前線シリーズ」を12年間にわたって放送してきましたが、彼女が日本看護協会としてさまざまなカタチで支えてくれました。彼女がいたからこそ、番組を継続することができたと言っても過言ではありません。そんな人に私が看護の何を教えると言うのか・・・。彼女の名前が名簿にあるだけで、逃げ出してしまいたい衝動にかられたほどです。
日本看護協会からはさらにベテランが来ています。生田惠子さんは45年間、保健師として働いてきて、日本看護協会の理事を8年間も務められました。最近は看護大学で教鞭を執られていたと言いますから、先生が生徒になったということです。その旺盛な学習意欲には圧倒されてしまいます。
つい先日、私も参加したナースオブザイヤーの表彰式で、見事、今年のグランプリに選ばれた菅原由美さんも院生です。訪問ボランティアナースの会「キャンナス」の代表として、ナースひとりでも開業できるようにと活動を続けておられます。看護界では知らぬ者がいないと言ってもいいような有名人で、講演活動もなさっていますから、学ぶ側というより教える側が似合う人です。
他にも、ナースや大ベテランの助産師や理学療法士、カウンセラーなどがいますが、ITの専門家の男性もいて、多彩な顔ぶれとなっています。私が実際に教室で教えるのは、前期に2回だけ、2コマずつの計4コマで、医療ジャーナリズムコースの大熊由紀子教授の講義の中の一部を担当するという形になっています。大熊さんはもともと朝日新聞の社会保障系の名物論説委員でしたが、この医療ジャーナリズムコースは元読売新聞の水巻中正さんや丸木一成さんなど、社会保障を専門としたトップジャーナリストたちが名を連ねていて、他にはないユニークなコースとなっています。
私以外はみんな活字系の人ですから、私はあえて映像表現の分野を担当しています。同じグループでもある「医療福祉チャンネル774」(スカイパーフェクTV)の「黒岩祐治のメディカルリポート」と連動させた講義にしようとあれこれ知恵を絞っています。院生に番組の企画を出してもらい、うまくすればそれをそのまま番組にして放送するようにしています。
番組作りという土俵にいるかぎり、大物院生たちに向き合うこともできるだろうと、先日、腹を括って講義に臨みました。事前に企画書を制作しておくようにと宿題も出してありましたので、ひとつひとつプレゼンテーションを聞きながら、それを講評し、番組そのものにしていくための課題について議論していきました。
さすが、それぞれの専門家のみなさんだけあって、思いのこもった企画書が出来上がっていました。しかし、それをひとつひとつ吟味していく過程で、私が教える側に回っている意味を自分でもつかめるような気がしてきました。それは日常的に私が「新報道2001」のスタッフとの間で行なっているやりとりと大差ないものだったからです。
プロのディレクターであっても、最初から完璧な企画書など作れるものではありません。最初はテーマだけは提示されていますが、それを具体的にどういう番組にしていくかについては、漠然としているのが普通です。ただ、そのままでは番組にはなりません。ディレクターからプレゼンテーションしてもらった企画について、スタッフと喧々囂々の議論を重ねてカタチを作り上げていくのです。
院生から提示された企画の中にたまたま終末期をテーマにしたものがいくつかありました。しかし、一言で終末期と言っても、茫漠としすぎていて、どこからどう手をつければいいか分からなくなってしまいます。そのテーマだけで何冊も本が書けるような話しです。私が番組作りの最初に、いつもスタッフと議論するのはどういう「切り口」で、この問題を扱うかということです。

番組というものは大きなテーマを独自の「切り口」で切って見せることが大事です。あれやこれやと論じるのではなく、「切り口」を決めて、その角度からそのテーマ全体を考えるようにするのです。「切り口」があいまいなまま、制作を始めようものなら、自分でも何が何だか分からなくなって、混乱してしまいます。
たとえば、ある院生の企画書のタイトルは「死に方に関する多様な価値観」となっていました。修士論文のタイトルならそれでいいでしょうが、テレビの番組としては成立しません。なぜなら、「切り口」が見えないからです。多様な価値観をどういう「切り口」で切って見せるかが勝負なのです。「多様な価値観」についてあらゆる角度から議論すればいいいではないかと思われるかもしれません。しかし、「多様な価値観」があるからどうなんだ、何をどうしようというのかが提示されていないと、かみ合った議論にはなりません。
「切り口」が決まらない企画では、具体的にどこに取材に行って、何をカメラに収めればいいのか、誰にインタビューすればいいのか、スタジオ討論の論点は何か、それにふさわしいスタジオゲストは誰なのか・・・。何も見えてきません。
その院生の企画書の中には「切り口」らしきものがないのかなと思ってよく読んでみると、「デス・エデュケーション(死の教育)」という言葉がありました。私は直観的にこれは「切り口」になりうるんじゃないかと思いました。私は院生の看護のプロたちに問いかけました。「看取りをやっている訪問ナースたちはデス・エデュケーションを受けているのか?」「看護教育の中では行われているのか?」「医学部教育の中ではどうなのか?」
そもそも「デス・エデュケーション」とはなんなのでしょうか?医療・看護のプロたちだけが受けるべきものなんでしょうか?本来は家庭の中における親子の会話の中にこそあるべきものなのかもしれません。私が日野原重明先生と組んで10年間にわたって上演し続けているミュージカル「葉っぱのフレディ」は葉っぱの死を見つめることによって、いのちを考える物語です。それも「デス・エデュケーション」ではないでしょうか? 「デス・エデュケーション」とは実は「いのちの教育」と同義なのかもしれません。
これを「切り口」と決めると、番組としてはたとえば「デス・エデュケーション不在の看護教育を問う!」とすると、立派な企画書に仕上がるのです。そうすると、どこに取材に行って、何をカメラに収めてくればいいのか、誰にインタビューを取るべきなのか、スタジオのゲストは誰がふさわしいかなどが、見えてきます。その議論の中で「死に方に関する多様な価値観」を織り込んでいくことは十分に可能です。
以前にこの欄でも紹介したことがありましたが、これまでに2人の院生が自分の企画の放送にまでこぎつけました。二人とも「切り口」を見つけるまでがたいへんでしたが、その後も話が広がりすぎてしまう傾向があって軌道修正するのに苦労しました。私とプロの制作スタッフがサポートするんですが、私たちにとっては、自分たちで企画して制作した方がよほど手間ヒマかからずにできるのです。しかし、自分の企画が番組になって放送されることの感動を味わってもらいたい一心で、サポートしています。
今回の院生の中から、どんな番組が出来上がってくるか、今からとっても楽しみです。