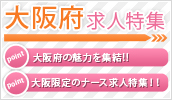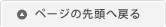第20回 スーパードクターエッセイ/水沢慵一
スーパードクターエッセイ

第20回 「コミュニケーション」という最先端医療技術
今年の東京の冬は久しぶりに雪の多い冬です。雪の前後には暖かい日があったり、気温の変動がおおきいので、私のクリニックにも調子を崩した子ども達がひっきりなしに訪れます。昨年と同じように麻疹の流行の兆しも見え、なんとなくおかしな気配です。
考えてもみれば、麻疹が流行するというのもおかしな話です。予防接種はいったい何のためなのか、本来こどものうちに罹っておくべき病気を大人にまで持ち越すとは、どういう意味があるのでしょうか。答えなどない疑問ですが、そんなことを思い巡らしたりするこのごろです。
さて、今回は医療現場におけるコミュニケーションについてお話しさせていただきたいと思います。過日、友人からおもしろい本があると教えられ、神戸女子大学の教授で、フランスの構造主義がご専門の内田樹氏と、三軸修正法という整体のような代替医療技術の専門家である池上六朗氏の対談をまとめた書籍に出会いました。 『身体の言い分』(毎日新聞社・2005年)という本で(価格も手頃なので、皆さん、ぜひ読んでみてください)、その中で内田氏の興味深い話が紹介されています。
要約しますと、内田氏が教鞭をとっておられる神戸女子大学は文科系の大学であるのに、そこへ、もともと医学部で教鞭をとっていた教授が移籍なさってこられた…。なぜ、理科系の医学を教える教授がわざわざ文科系の大学に移るのか?それは、今の医学部学生たちに対してがっかりしたから…だというのです。
何がそんなに彼をがっかりさせたのか?それは、医学部生のコミュニケーション能力があまりに低すぎるということなのだそうです。医学生たちの質問の多くは「このポイントが試験に出るかどうか」であり、医学そのものへの関心でもなく、医学の単なる知識を越えたところへの好奇心でもない、ということなのです。
それがゆえに、実際に非常に限られた時間しかない患者さんとの問診会話の中で、本来なら見つけ出せてしかるべき病気が見つけられない。少なくない検査をして、その結果データを見てばかりで、患者を診ていない。患者の口から聞けばすぐに診断名に見当がつくはずである有機的な情報(ライフヒストリー)を引き出せない。…そして、ついには、これは由々しき事態となり、医学部の必修科目に「コミュニケーション基礎講座」なんてものまで設けられてしまっている、ということなのだそうです。
この本の中で、内田氏は患者とのコミュニケーションの重要性を説いておられますが、これは私が現場で感じているまさにそのことなのです。これまでの寄稿において私は何度も、患者の言葉にならない情報を汲み取り、患者たちも気がついていない「理由」や「原因」を引き出していくことがいかに重要なことかをお話ししてきました。これは、診療において本当に大切なことで、だからといってどこかで教えてくれたりすることでも、教科書を開いて勉強すれば身につくことでもないのです。
しかし、それができない医学生達が医師となり、生身の人間である患者さんたちを診断していく。これまた今の医療現場の現実です。
この「コミュニケーションの薄さ」は、一体どこからうまれてきてしまうのか…ということについて内田氏は独特の表現で語っています。本来コミュニケーションというのは、発せられる言葉の過去と未来をイメージして行われるものであるけれども、この過去と未来の時間的な幅が、実に狭い人が少なくない数いるというのです。
「空気の読める人」「カンのイイ人」というのは、発せられる言葉のその先をイメージする力が豊かにある人であり、「ニブい人」というのは、そのイメージ力が貧弱で言葉の質量がとても小さい…(内田氏の表現の通りではありませんが、私はそう解釈しました)と内田氏は言っています。それは、目の前にいる患者さんが発する言葉の前や後ろに隠れている…ひょっとしたら医師から見つけてもらうのを待っている、まだ発せられていない言葉たち…を引き出したり、言葉以外の身体感覚や情報として見つけ出して拾っていかなくてはならないものなのです。これは、武術的な身体論にも通じるのだとか。
しかしながら、いまの医学部教育では、多くの若い学生達が育ってきた核家族という生育環境や偏差値教育などの弊害がたまって、医師の人間的な技量の低下を招いているのではないでしょうか。医療技術、特に先端技術はめまぐるしく進化し、人間以外が行う部分は実にすすんでいます。しかし、技術進歩より以前に、私たち医師は「生身の人間が生身の人間に接する仕事」なのです。
検査データには出現しないソフトな情報を患者さんたちからいかに引き出してキャッチするか、これは診療において必要不可欠な専門技術のひとつと言えるでしょう。名医といわれる医師たちは、決してデータや写真から診断名を教えてもらうわけではありません。データや写真と診断名をリンクさせるのは、医師の有機的な目です。患者の言葉やしぐさ、色つや、匂い、雰囲気など様々な情報から「アタリ」をつけ、それをデータの中に見つけ出していく。このプロセスは、未熟な医師が陥りがちな「病名から現実をあてどなく探す」というやり方とは180度反対の方法。患者さんという「現実」が先に存在して、それを診断名へとおとし込んでいく、つまり真逆のプロセスなのです。
このプロセスは、小児科に限らずどんな場合でも(医療以外でもそうでしょう)当てはまるものですが、特に小児科は、しっかりとした表現主体を未だもっていない子どもや赤ちゃんが主人公であり、そこに保護者のフィルターがかかって、医師の眼前に繰り広げられる現実は実に複雑で豊かな情報を与えてくれるのです。
未知のものを不安や恐怖として避けてしまうのではなく、謎解きをしていくような楽しみを見つけられると、小児科診療ほどおもしろいものはないと思います。
うぅーん、そう思うと…だから、小児科ってやめられないんですよね!
さて、そんなことを考えながら、麻疹の流行も気になりつつ…そうです、麻疹の診断も同じく、診断に必要情報をどう見出すかにかかっているのですが。
もう来月は春ですね、花粉も気になるところですが、みなさん体に気をつけて頑張りましょう!