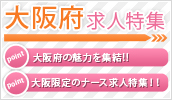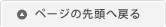第18回 スーパードクターエッセイ/水沢慵一
スーパードクターエッセイ

第18回 全感覚を集中して「観察する」
先だって、教育関連の専門雑誌社から「いじめ」に関する記事の依頼がありました。といっても私は小児科医ですので、内容としては「いじめ」の発見や未然防止につなげられるために、子どもの心身の状態を把握するヒントのようなことを……ということで、執筆にあたって改めて子どもを観察することの大切さを感じました。
それは、いつもの診療において無意識に行っていることではあるのですが、診察室の中のほんの短い時間のなかで、患者である子どもと親御さんと向かい合うとき、「集中して話を聞く」ことが、いかに重要であるかということです。
私たち医師の問診は、一般的に医療的で無機質な質問となるのはいたし方のないことですが、その質問ひとつひとつにエネルギーを込めるというのは、有機的な仕事です。私のクリニックを訪れる子どもたちの多くは生まれたばかりのホヤホヤで、言葉を理解するどころか、縁あって生れ落ちてきた人間界の空気に馴染むのにやっとという程度の人生の超ビギナーたちです。そんな赤ちゃん達に向かっては、言葉は実に無力です。となれば、その親御さんたちにとっても同じく、子どもと向き合うとき言葉は意味のない道具と成り下がってしまいます。
それは、親御さんたち自身が新しい家族を迎えてから痛切に感じていることだと思います。特に最近では30代での出産はあたりまえで、お母さんとなる女性も、お父さんとなる男性も、社会とのかかわりも長く深くなって、大人としてのコミュニケーション方法にすっかり慣れ親しんできた人たちが、あるとき突如として言葉の通じない宇宙人と暮らし始めるのです。もちろん、妊娠期間中の一年近くは、特に母親と胎児の心のコミュニケーションは不思議な力を秘めたものではありますが、一旦おなかの外の世界へと鳴り物入りで登場した小さなスーパーヒーローは、親の疲労も一向に構わずにスグに泣いては、スグにグズって、あれをやってもこれをやってもご機嫌の治る風もなし……という状況に親は対峙させられてしまうのです。
そんな状態を考えてみると、いま中学校や高校生活を謳歌する多感な子どもたちも、身体のサイズと機能の差こそあれど、中身はその昔しっかりと親の手をわずらわせてくれた、小さくて未熟でありながら完全なスーパーヒーローに他ならないのでしょう。小さな赤ん坊たちも成長すれば、言葉を覚え自身の身体を思いの通りに操ることを覚え、まるでなんでも自分ひとりできるような錯覚に陥りますが、実際にはそんな器用になんでもできるわけはないのです。
以前に何かの書籍で読んだことがありますが「成人30歳説」というのがあるようです。それは、現在では成人というと20歳で、ハタチになって初めてたばこもお酒も晴れて許されるということになっていますが、その考え方によると実際に心身の最低限の免疫機能が整うのは30歳なのだそうです。
30年をひとくくりにするという考えは、実際的にも社会通念と通じる部分があるように思います。社会人といっても、20代はやはり未熟で様々な経験をして、30歳頃になって初めて自分の向き不向きを知り、60歳にもなると家族や社会との関わり方や立場が変わっていく。大きな問題となっている学校での「いじめ」問題の主人公となる子どもたちは年齢として15歳前後。30歳成人説をとれば、最低限の機能が備わるとされる未だ半分の道のりしか歩んで来ていないのです。
「半分」しか生きていないというのを他に例えれば……小学校入学の6歳の半分と言えば3歳…。出産の半分と言えば、まだ五ヶ月(胎児は骨格や筋肉がやっと発達してくる頃)…。
酸いも甘いもわかる60歳の半分といえば30歳。そう思うと、「半分」という質量がいかに脆弱であるかを想像するのは決して難くはありません。
これまで、子どもたちは急激な経済成長と経済不振、そのなかで繰り広げられる家族劇場、社会劇場のなかで力以上の役を押し付けられてしまったのかもしれません。いや、押し付けられてきたのを「これ以上はできないんだ…!」と悲鳴をあげているのでしょう。それは、子どもだけに限ったことではなく、家族を力の点から分解した時に、底辺にあたる子どもたちがそうであるなら、つまりは、その上に折り重なっている家族である乳幼児、高齢者、母親、父親にも悲鳴があがっているはずです。
いじめ問題は決して子どもだけの問題ではなく、家族全体、社会全体の波がとどいてくる、汚れてしまった波打ち際なのかもしれません。波打ち際は、長年見てみぬフリをして溜められた浮遊ゴミで汚されてしまっているようです。ハタチが成人というのも、経済効果を鑑みてのことなのかも知れず、そう考えると大人が勝手な都合でカネのなる木を作って、勝手な都合でダメにしたのかもしれません。
さて、冒頭にあげた教育関連の雑誌の寄稿において、私が書かせていただいたことは、言葉なぞ何の意味も果たさないような子どもとのコミュニケーションにおいて大切なのは、「観察」であるということです。その「観察」とは、単なる虫眼鏡や望遠鏡の観察ではなく、いってみれば、自身の全身をもって、相手の全身を観て、感じるということです。
小児科を訪れる、生まれたばかりの小さい乳児。病状を母親から聞くわけですが、しかし、実のところそれだけで診断がつくばかりの分かりやすい症状ばかりではありません。お母さんから話を聞いていると、ふと、逡巡する考えが真空状態にストンッとおちる点に出合います。その瞬間に得た診断名は、顕微鏡を使った詳細な検査や血液検査の結果とおもしろいほどに一致します。この体験は私にとって日常的なものですが、西洋医学という数値と分類の医学にありながら大変ふしぎな体験のひとつです。
今日の医療技術のめまぐるしい発達を裏支えしているさまざまな基礎研究やそれらを統合する研究者のみなさんのご苦労は大変なものだと思います。そして同時に、彼らのような最先端の技術開発は、頭のなかで想像できるレベルの数字の組み換えや発想法では届かない理性を超えたところにブレイクスルーがあるということも、過去の偉人達の自伝などから想像するところです。どんなに理性的な仕事であっても、本質的な作業とはヒトという生物に与えられた本能的な感覚をもってプロセスさせる領域にあるのではないでしょうか。
「子どもを観察する」に話をもどしましょう。
宇宙人のように見える子どもたちと接するときに、小手先の会話術のようなものを使ったところで効を奏するわけがなく、まず相手を「見る」こと、相手を「観察」すること、それはつまり全身をもって相手の状態を「知ろう」とすることが大事なのではないか。そうやって自分の回路が開かれると、不思議な事に相手の回路も開くのでしょう、何かが合い通じる瞬間を感じることができます。
私は、医師として、患者を前にしたとき一方的な感覚だけをもって的確な診断を下すことができるわけではないのです。診断を下すという感覚ではなく、診断名をおしえていただくという感覚に近いとも言えるかもしれません。自身の感覚を相手に集中すると、その真剣さが相手に伝わるのか、生き物同士としての電気的なつながりが生まれて相手から答えがかえってくる……そんな感覚です。
教育現場であれ、医療現場であれ、人間同士のコミュニケーションに根本の差はないでしょう。医師であれ教師であれ、子どもたちを前にして学校で学んだ知識で闘おうとするのではなく、患者である子どもたちや親御さん、生徒の心身の声に全感覚を集中させメッセージを受けとめる。長年現場にいてもその作業がうまくいったときの悦びはいつも新鮮に私に訪れます。
全身の感覚を総動員して相手を知ろうという姿勢は、愛情をもって相手を受け止めようとする姿勢に通じるものではないでしょうか。
うぅーん、そう思うと…だから、小児科ってやめられないんですよね!
もう新年がやってきます。年末年始の忙しい時期、健康に留意してお互い頑張りましょう。来年の干支はネズミ。小児科とネズミ…? そんなお話ができるといいかもしれません。
また次回、お目にかかります。