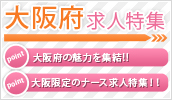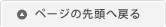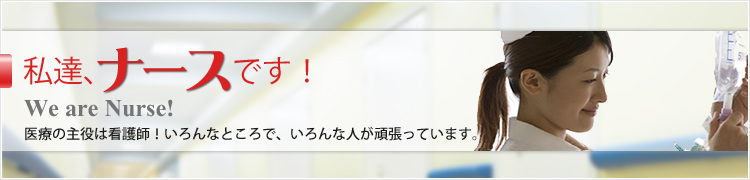
私達ナースです(看護師の声)
私達ナースです(看護師の声)
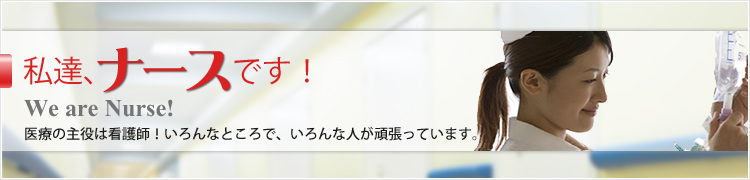
Vol.18 回復リハビリテーション病棟での看護業務 荻原みさき病院 看護部長 宮本 しげ子さん

回復リハビリテーション病棟での看護業務
荻原みさき病院 看護部長 宮本しげ子さん
荻原みさき病院は神戸市兵庫区にあり、もともと整形外科を中心とする急性期病院であった。
ところが、介護保険制度の導入にあたり、急性期病院から療養病床、回復期リハビリテーション病床へと切り替えを図った。
その変革を看護部長として牽引したのが、今回ご紹介する宮本しげ子さんである。
宮本しげ子部長は1943年に兵庫県で生まれた。現在の丹波市である。中学生のとき、お母様と中学校の担任の先生から看護師になることを勧められ、兵庫県三田市にあった国立療養所附属の准看護学校に入学する。卒業後はその国立療養所に勤務したが、3年目になったときに神戸市の社会保険病院に移った。そこで、キャリアアップを実現するため、京都市の社会保険病院に附属していた高等看護学校で学び、正看護師の免許を取得した。
その後、結婚し、1969年に長女を出産する。出産後は神戸市の済生会病院に移り、准看護学校で教務の仕事に就いた。「教務の仕事を20年しました。看護とは何かということを後輩たちにいかに教えていくか考え続け、やりがいのある毎日でしたね。当時は家庭に掃除機などが普及した頃で、中卒の生徒たちの中にはほうきが使えない、雑巾が絞れない子もいたのです。そういったしつけから始めました。教育ができ、信頼関係が強まると、強い絆ができます。今、私どもにはそのときの教え子が4人も勤務しているんですよ。」
 1987年に済生会病院は神戸市北区に移転することになり、准看護学校の閉鎖も決まった。そこで、宮本部長はかねてから興味のあった老年看護の実践の場を求めて、荻原みさき病院へ入職を決意する。「当時はまだ医療行為をすればするだけ、お金になった時代でした。現在は99床ですが、その頃は123床あり、今とは全く雰囲気が違いまして「臭い、汚い、暗い」という3K職場そのものでした(笑)。付添婦さんと呼ばれる人たちがたくさんいて『ここに看護はないのか』と驚きました。」
1987年に済生会病院は神戸市北区に移転することになり、准看護学校の閉鎖も決まった。そこで、宮本部長はかねてから興味のあった老年看護の実践の場を求めて、荻原みさき病院へ入職を決意する。「当時はまだ医療行為をすればするだけ、お金になった時代でした。現在は99床ですが、その頃は123床あり、今とは全く雰囲気が違いまして「臭い、汚い、暗い」という3K職場そのものでした(笑)。付添婦さんと呼ばれる人たちがたくさんいて『ここに看護はないのか』と驚きました。」
そこで宮本部長は付添婦の廃止という改革を行う。同時にヘルパーを育成し、病院で雇用するシステムを整備した。当初7人を募集し、ベッド周りの掃除の仕方、体の拭き方、おむつの換え方などを教育した。当時の厚生省(現 厚生労働省)も付添婦廃止の通達を出してはいたが、なかなか実現には至らなかったのが実情である。そして、新しい看護基準を取得するための看護師の数も絶対的に不足していたという。「そこで老人病棟の新設に踏み切りました。老人病棟では6:1でしたから、なんとか充足しそうだったのです。そして4:1のヘルパーを整備し、1994年に指定を受け、急性期病院の役目を終了したわけです。」
ところが1995年1月、阪神大震災に遭い、病院は古い棟が全壊してしまう。幸い患者さんに被害はなかった。看護部は3日泊まって3日休むというパターンの72時間体制を組んで業務に当たった。
「看護師の本能なのでしょうか、震災当日は休みの日だった若い看護師も使命感を持って続々と病院に駆けつけてくれました。私も通勤に使っていた神戸電鉄が復旧するまでは往復6時間かけて通いました。」
神戸市内の急性期病院はどこも満床となり、遠くの病院に移送された患者さんもいた。当時は118床だったが、ほぼ「雑魚寝」の状態だったという。さすがに「病院を閉鎖したらどうか」という意見もミーティングの場などで出されるようになってきたが、宮本部長は「これから、この病院が必要とされる時代になる」という信念を貫いた。
そして1996年に完全リニューアルを行った。さらに2000年の介護保険制度発足に向けて、新たな病棟編成に取り組むことになる。「私個人としてはケアマネージャーの資格を取得し、介護保険制度のもとでの看護に役立てようと思いました。それから介護病棟のための書類作成に忙殺されましたね。」
介護病棟に加え、神戸市で「笑顔の窓口」と認定されている居宅介護支援事業、訪問看護ステーション、訪問介護ステーションに、看護師5人、ケアマネ2人、登録看護師10人を配属した。「最終的な責任は私がとりますが、それぞれに現場での責任を持たせるような教育を行いました。」
 急性期病院が慢性期病院に変化するにあたり、現場の看護師の戸惑いはかなり大きかったのではないかと推察される。「急性期病院だと患者さんの容態の変化で器具を持って走り回るわけですが、老年看護はそうではありません。一番大切なのは終末期に向かう患者さんの家族に対してのケアなのです。家族の方々が大事な家族の一員を失おうとしているとき、看護師はどうあるべきなのでしょうか。看護師自身が死から遠ざかる嫌いがありますよね。夜勤のときに患者さんが亡くなったらどうしようという声も聞きます。そういうときこそ、これまでお世話した患者さんの最期を看取ることができる幸せを感じて頂きたいですね。」
急性期病院が慢性期病院に変化するにあたり、現場の看護師の戸惑いはかなり大きかったのではないかと推察される。「急性期病院だと患者さんの容態の変化で器具を持って走り回るわけですが、老年看護はそうではありません。一番大切なのは終末期に向かう患者さんの家族に対してのケアなのです。家族の方々が大事な家族の一員を失おうとしているとき、看護師はどうあるべきなのでしょうか。看護師自身が死から遠ざかる嫌いがありますよね。夜勤のときに患者さんが亡くなったらどうしようという声も聞きます。そういうときこそ、これまでお世話した患者さんの最期を看取ることができる幸せを感じて頂きたいですね。」
荻原みさき病院では、患者さんと家族の時間を多く作り、充実した看取りをサポートする体制を作っている。差額ベッド代も徴収せず、最期の2、3日をともに過ごしてもらったり、清めを家族とともに行ったりという内容である。清めにあたっては綿を詰めることもしないという。故人の本当の姿を尊重して、死後の処置に故人のお孫さんにも入ってもらうなど、家族のお見送りを重視する。
また宮本部長は身体拘束の廃止にも傾注してきた。荻原みさき病院では、身体的な安全や保護の目的から、ベッド柵4本、ベッド柵の固定、ベッド柵カバー、車椅子でのY字ベルト、つなぎ服などを使用してきたが、1998年の「抑制廃止福岡宣言」をきっかけに抑制委員会を立ち上げた。具体的な改善内容としては、ベッド柵4本から2本に削減し、転落の恐れのある場合にはベッドの下にマットレスや畳を敷いた。またアセスメントスコアの高い患者さんには介護ベッドを導入した。さらに、高齢者の座る能力に応じた座位保持を工夫し、膝の下に枕を入れたり、踏み台を使用するなどしてY字ベルトを廃止した。膝掛けを使用することで安心感にもつながっている。そして排便のコントロール、排尿パターンなどを知ることでオムツ交換の時間調整が可能となり、つなぎ服の廃止も実現した。
「医療行為とリスクは背中合わせとなっています。リスク回避にはやはりスタッフの連携が必要です。看護師だけでなく、ヘルパーも見回りをして、様々な情報を共有していかなくてはいけません。一人の患者さんの用事を済ませるだけではなく、ほかの安全管理にに目を配ってから詰所に戻ることも徹底させています。患者さんは『私のところに来てくれた』というのは嬉しいものなんですよ。」
療養型病床には病院機能評価がなく自己評価を行うにとどまっているのだが、全国170あまりの施設が参加して、サービスの質を競う制度があり、荻原みさき病院もここ数年参加している。
「最初は102番だったのですが、今年は33番まで順位を上げることができました。皆の意識を高めてサービス改善に努めていきたいですね。」
 2006年1月には回復期リハビリテーション病棟を34床で開設することになった。病院の西隣りに新病棟を増築し始めたところ、兵庫城の跡が出現し、思わぬ遺跡の発掘調査にもなったという。
2006年1月には回復期リハビリテーション病棟を34床で開設することになった。病院の西隣りに新病棟を増築し始めたところ、兵庫城の跡が出現し、思わぬ遺跡の発掘調査にもなったという。
この病棟では、宮本部長はソーシャルワーカーとしての業務もこなしている。医療連携室で電話連絡を受けると、チェックリストと呼ばれる情報提供書に記入をお願いし、その後面談を行う。そして判定会議にかけ、結果を報告する。「回復リハに関してはゼロからのスタートでしたので、チームを組んで四国の2つの施設に研修に行きました。それからOT、PT、STというセラピストの確保ですね。なんとか28人に来て頂きましたが、在宅リハもありますからフル回転ですよ。」
回復リハ病棟では看護師の役割も非常に大きいが、宮本部長は「まだ60点」と辛い点数をつけている。「なんらかの障害のある患者さんの障害がゼロになるということは難しいのです。そこで、どのように患者さんの日常を援助していくべきか、看護のあり方を考えないといけませんね。患者さんがご自宅に戻るのか、職場復帰できるのか医師やセラピストとの連携を丁寧にとり、患者さんの生活の再建をいい形でお手伝いするためにスタッフ全員の情報の共有は不可欠です。」
荻原みさき病院ではカンファレンスを徹底して行っている。医師、看護師に加え、OT、PT、ST、ヘルパー、管理栄養士も加わり、週2回、1回につき4人ずつの患者さんについて詳細な報告がなされている。そのため、看護師の観察力が向上してきたという。「若くて敬語を上手に使えない看護師でも、患者さんにすーっと入っていける能力があり、感心しています。このカンファのおかげで、治療プログラムの策定もうまくいくようになりました。」
最後に宮本部長に、メッセージを頂いた。
「急性期であれ、慢性期であれ、看護師がするべきことの一つがメンタルケアです。回復リハの場合は患者さんの社会復帰への支援のあり方が肝要です。そして療養病床の場合は家族のメンタルケアですね。家族の死をどう受け止め、喪失感をどう受け止めるのか、看護師の役割は大きいです。そして組織への帰属意識を持つこと。まず仕事を好きにならなくてはいけません。自分の仕事に誇りを持てば、いい仕事につながっていくと信じています。」